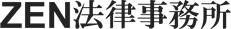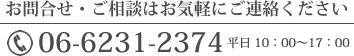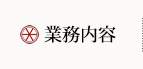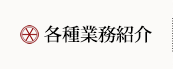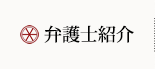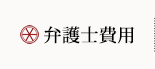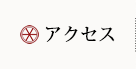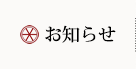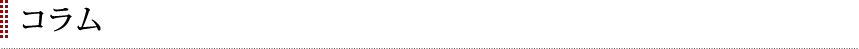- 2025-09-26
- 著作権法について⓶
5 「著作権」とは?
著作物を創作した人(著作者)は、①著作権(財産的な利益)と、②著作者人格権(人格的利益)を有することになります。
著作権は、著作者の死後70年維持され、自由に第三者に譲渡することができます。
他方、著作者人格権は、著作者の死亡により消滅し、第三者に譲渡することができません。
6 著作権の内容
「著作権」は、複数の権利(支分権)で構成されています。
上記の権利の内容は多岐に渡りますが、原則としては、下記のような行為が禁じられています。ただ、他方で、「例外」も複数定められており、例外にあたる場合には著作権侵害にはなりません。
第三者の行為が著作権侵害に該当するときには、当該著作者から差止請求がされたり、また、損害賠償の請求がされる可能性があります。
⑴ コピーの作成
⑵ 公衆に対面で提示(上演・演奏、上映、伝達、口述、展示)
⑶ 公衆に送信
⑷ 公衆にコピーを提供(頒布、譲渡、貸与)
⑸ 二次的創作物の創作・利用
7 著作物利用の例外
上記の通り、著作物を無断で複製することは禁止されていますが、「例外規定」に該当するときには、著作権侵害にはなりません。
例えば、「私的使用のための複製」であれば許容されます。
個人利用又は家庭内での利用等といった限られた範囲内における使用であれば、著作物を複製することも許されます
つまり、「私的使用」を超える場合は、著作物を複製することは許されません。
また、他人の著作物を「引用」して利用する場合には、著作権侵害にはなりません。
ただし、その利用が「引用」であることが分かるようにする等、引用としてのルールを順守する必要があります。
8 著作者人格権について
著作者人格権は、①公表権、②氏名表示権、③同一性保持権から構成されています。
「公表権」は、未公表の著作物を公表するか否か、また、公表のタイミング等をコントロールする権利です。第三者が、未公表の著作物を無断で不特定多数の者に対して提供や提示等をすることは許されません。
「氏名表示権」は、著作物が公表される際に、著作者としての氏名(又はペンネーム等)を表示するか否か等について保護されます。
「同一性保持権」は、著作物に対する改変を禁じる権利です。
上記の著作権同様に、➀~③のいずれかが第三者によって侵害されたときには、差止請求及び損害賠償請求の対象となります。
9 契約実務について
上記の通り、著作権や著作者人格権は、複数のルールが絡み合っています。
その為、ビジネスにおいては、知らないうちに著作権侵害を犯していることも有りえます。
そうならない為にも、契約書で著作権の所在を確認したり、著作者人格権を行使しないことの確約を取り付けたりする等といった対応が重要になってきます。
弁護士 久岡秀行
Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.